- Home
- education, privatework
- 職業体験(1日目)
職業体験(1日目)
- 2011/11/24
- education, privatework
- コメントを書く
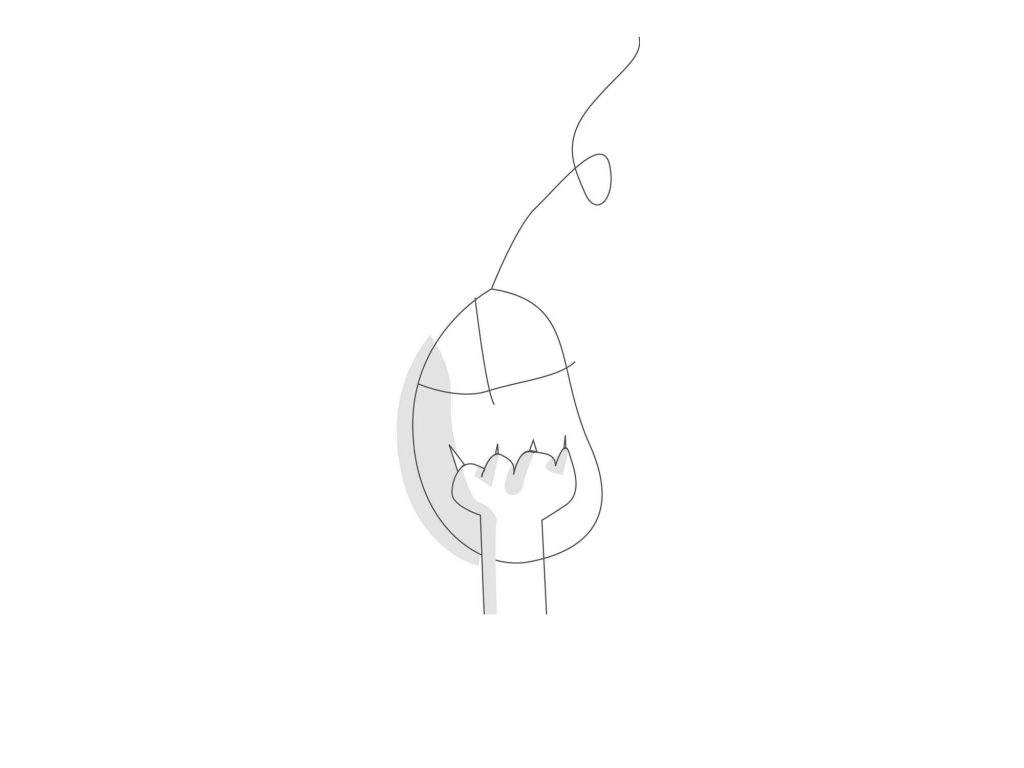
お久しぶりです。
前回からの間、仕事を一生懸命こなしたり、古傷の靭帯をしこたま痛め病院にかかっていたりと、何かと落ち着かない毎日ではありましたが、本日ようやく職業体験の1日目をこなして来ました。
今日は、その報告。備忘録なので、やたら長いです。
「校長先生からホームページの改修を依頼された」という前提で始めた今回の職業体験。本日は1日目ということで、以下の作業をこなしました。
・ブレーンストーミングによる意見の抽出
・KJ法を用いた意見の集約と、戦略の立案
・役割決め
・構築作業
まずブレストでは、僕が議長となり、予め宿題としておいた「ホームページの改修案」を集めながら、意見出しを行いました。
デザインに気を向ける子、アクセスカウンタや画像の処理などの技術にこだわる子も確かにいましたが、「部活動の紹介や、大会での実績が必要」「委員会活動の内容も欲しい」「同窓会へのリンクは貼れないか」「先生の紹介も欲しいよね」など、前回僕が話した趣旨をキチンと消化した意見も多かったです。
他には「画像が少ない」「動画や音声(合唱)も欲しい」などの意見が上がりました。
これをKJ法でまとめる作業がちょっと難航。意見を集約していくという過程の難しさがある程度わかってもらえた時点で、ここは少し手助けをしました。でも、KJ法のうち「グループ編成」の中頃まで進めたので、まあ及第点じゃないかと思います。
その後、僕が予め用意しておいたJimdoのテストサイトを公開し、その上で役割分担を決めました。
提示した役割は以下の通り。
・ディレクター(2名)
・ウェブデザイナー(2名)
・グラフィックデザイナー(2名)
・ライター(3名)
jimdoのサイトを見せた瞬間から、触りたくて仕方がない子供たち。なにせJimdoは簡単だし、楽しそうだからね。でも、意外とグラフィックデザインやライターにも人気が集まり、結局は僕がディレクターを指名する形でまとまりました。
ちなみに、僕はプロジェクトマネージャという位置づけに入りました。もちろん、アドバイスはするけど手は出しません。
ここからディレクター、ウェブデザイナー、グラフィックデザイナーに仕事のキモと簡単なミッションを与えたところで午前中が終了。
聞いた事のない役割を与えられた生徒たちは結構戸惑っていましたが、性格の悪い僕は、午前中の終わりに、わざと他の役割と作業が被るようなミッションを与えました。個人的に、仕事ってのは役割が被った部分をどう調整していくかが大切だと思うので。
在校時よりも遥かに美味しくなっている給食をいただき、ひとしきり先生と話したところで午後に突入。教室に戻ると、生徒達はみんなで揃ってワイワイとウェブサイトを並行更新。予想していたことですが、みんなウェブサイトが触りたいみたいです。
午後一でライターの子供達を呼び出し、作業を指示。
ライターに与えたミッションは、「読む人の事を考えて記事を書け」「これから書く人々の参考になるような記事を書け」という二点です。性格の悪い僕は、更に「Googleから人が呼び込めるように、キーワードを意識して書け」だの「大見出し、中見出し、小見出しの階層を意識して書け」だのと揺さぶりをかけます。
これは、ライターとしての資質がある生徒を見つけるため。案の定、殆どの生徒の手が止まる中、1人の生徒がこの作業指示に基づき作業を始めました。先が見えない中で、とにかく手を動かすというのは重要なアプローチです。
残る二人の生徒は先陣を切って作業を始めた生徒に習い、見よう見まねで作業を開始しますが、すぐにネタが尽き、ディレクターにコンテンツの提供を求めます。散々、ディレクターがこき使われた後で、「ライターなら自分の足で記事を取ってこいよ〜」と指示を出しました。
そういうと彼らは「あっ、そうか」と気づき、自ら先生達のインタビューに向かいました。
一方この間、グラフィックデザイナーは校内の撮影に走っていました。僕のD300を貸し、外から見た母校の売りを幾つか話した後で、「じゃ、撮ってきな〜」と無責任に送り出したのですが、彼女らは小道具やアングルに凝った、面白い写真を幾つも撮影してきました。
この写真をみんなで共有すると、追加で必要な素材がライターやウェブデザイナーから発注され、彼女らは楽しそうに撮影に向かいました。彼女らは、何の指示を出さなくても自立的に動ける、頼もしいプレイヤーです。
その頃、ウェブデザイナーは。
サイトを自由に改変できることの楽しさでハイになり、暴走していましたw
そして、ディレクターはディレクションが出来ずに途方に暮れていましたw
まあ、そう仕向けたのですから、当たり前ですwww
ここで、ディレクターに向けて、ディレクションとプレゼンに関する秘策を教えました。ま、昔の上司の受け売りなんですけど。それは、こんな秘策です。
・社長とヒラ社員が見えている世界は違う。そして、プレゼンテーションを聞くのはヒラ社員ではなく社長。
・細かい事柄に惑わされず、ディレクターはディレクション(方向、ベクトルの向き)を意識しよう。
・社長(ここでは校長先生)と、君たちの共通のディレクションは何かと言えば、「ホームページをお客さんの役に立つものにカイゼンすること」
・ホームページのお客さんを全て洗い出し、それぞれのお客さんの役に立つコンテンツを、ブレストのアイデアから一つずつ抽出しよう
・今あるコンテンツ、作成中のコンテンツのうち、役に立つお客さんがあるコンテンツは優良コンテンツ。誰にも向いてないものは不要なコンテンツ。そして、必要なのに作成されていないのが、ディレクターが他のメンバーに求めるコンテンツ。
この説明でようやく方向性が見えたディレクター達は、こんな答えを用意しました。
・これから中学校に入る6年生→部活動紹介
・地域の方々→地域のニュース、生徒自身が書く日記
・OB/OG→今の高柳中学校の情報、同窓会リンクページ
・保護者→行事の告知、報告
・生徒→先生の情報(例えば新任の先生)
・先生→委員会の活動
・未来のOB/OGたる自分自身→年度毎に分かれた記録ページ
まあ、立派なものです。
ここで方向感の定まっていなかったウェブデザイナーを招集。ディレクターの考えを伝えた上で、彼らには「これらのコンテンツを、冗長化させずに、適切なページに配置するための仕組みづくり」を考えるように指示しました。
彼らは最初、僕の言う意味をよく理解できなかったのですが、ここで彼らが散々遊んでいたブログの設計方法をじっくりとレクチャー。ブログのカテゴリー分けと、カテゴリーで抽出することによる1エントリーのマルチな利用について教え、ブログにカテゴリーを振る事により、必要なページに必要な情報を出力する仕組みを自ら考えだしました。
ここは意味分からないかもしれない。
例えば、トップページに出力するためのカテゴリー「新着情報」と、各部活単位に出力するためのカテゴリー「(例えば)サッカー部」などをエントリーに設定する事により、「サッカー部の試合結果」と言う記事は、トップニュースにも、サッカー部の個別ページにも出力されるようになります。
・・・説明しても意味わかんないね。
この辺りで、既に約束していた14:30に近づく。
「もう終わりだけど、どうする?」と聞くと、「先生、いつまでならできるの?」と返事がきたので、結局16:00まで付き合うことにしました。
その後、ライターには「全ての記事を君たちが書くのは大変だから、カテゴリー単位で記載ルールを作り、それぞれ所属している人に書かせる工夫をしてみれば?」とアドバイスを送り記事を構造化。
ディレクターには「君たちのプレゼン自体も大切な資源になる筈だから、プレゼンの内容はwebページに仕込んでみれば?」とアドバイスしました。
また、写真を撮り終え、仕事がなくなってしまったグラフィックデザイナーには、「明日、ホームページのロゴを制作しような」と約束しました。
こんな感じで1日目が終わり。
彼らは家に帰って仕事の続きをやり、明日は15分登校を早めるそうです。面白いね。
僕が密かに面白いなあと思ったのは、誰にも指示されず(いや、むしろ指示を無視して)、ひたすらカレンダーの表組をしていた子。彼は僕のアドバイスを一切聞かず、他の子の作業にも一切目も振れず、「これが俺の仕事」と決め込んで黙々とカレンダーを作成していました。
でも、これが結構凄いのよ。
即戦力になるのは、実は彼みたいな人材なのかもね。
さて、明日はいよいよパイロット版のアップと、プレゼンテーション。既に先生の中では結構話題になっているみたいで、校長先生しか招待していなかったプレゼンには、何人も先生が訪れるようです。
彼らには結構なプレッシャーでしょうが、良い経験になればいいなあと思います。
では、結果はまた明日報告します。



















