- Home
- education, privatework
- 職業体験としてのPTA文化事業(開催顛末編)
職業体験としてのPTA文化事業(開催顛末編)
- 2013/12/11
- education, privatework
- コメントを書く
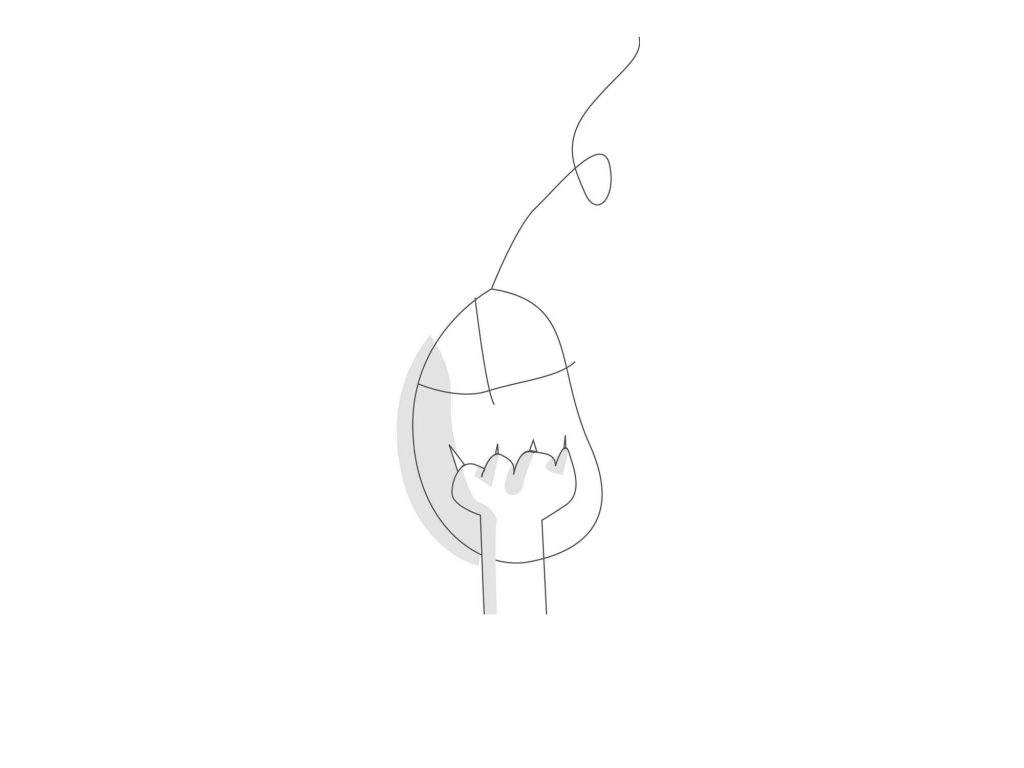
はじめに
公開するかどうかは思案のしどころだったが、まあ特定されないレベルであれば問題あるまい。
どこかで精査しておかないと先々に後悔する気がするので、忘れないうちに書き留めておく。
もはや、プロジェクトマネージメント。完全に仕事モードだった。
というわけで以下、詳細に過ぎて誰かの役に立つとは思えないが、僕の役には立つ。
仮にこの記事を読み「本校でもチャレンジしてみよう」と考えたPTAの方がいらっしゃるのであれば、出来る限りの協力は惜しまないつもりです。
ただし、読んで想像している以上に大変なので、僕にコンタクトを取る前に死ぬ覚悟を決めてください。
文化事業とは
本校PTAでは2年に一度の行事として文化事業なるものを開催している。文化って何だよ?と思いつつ、今年度は前回を踏襲する形で本校版の◯ッザニアを開催した。伏せ字が入るのは大人の事情であり、わざわざ豊洲方面に名称使用許諾の依頼をかけ、見事に断られた経緯がある。まあ、依頼をかける方もかける方だと思う。
まあでも、要はキ◯ザニア。
それ相応に企画・準備が必要となる。
企画主旨
- 子供たちに職業体験の場を与え、仕事の楽しさ・大変さを体験させる。
- 体験の見返りに模擬紙幣を提供し、紙幣に基づく「レクリエーション」「自己研鑽」を可能とする。言わば「使う楽しみ」。
- 職業体験/自己研鑽のアサインについては、事前募集により予約する他、当日の飛び入り参加も可能とする仕組みを構築する。
- 職業体験の協賛店舗は基本的に地元の地公共/企業/団体およびPTA保護者から招聘する。
- 協賛者にも何かしらのメリットが醸成できるよう取り計らう。
- 本事業により死者を出さない。
- 最後は当たり前に聞こえるかもしれないが、これは大切なポイント。特に今回は飲食を扱うブースが多かったので、衛生面は予算をケチらず入念にリスクコントロールした。
出店内容
- 職業体験(7ブース)
- ダンサー(地元ダンススクール)
- 消防士(地元消防署)
- 車体整備士(某企業CSR部)
- 整体医院(地元整体院)
- 看護師(看護師である保護者)
- 新聞記者(地公共職員)
- 獣医(地公共職員)
- 模擬店 兼 職業体験(6ブース)
- カフェ(地元非営利団体)
- 餅屋(本校学童)
- 焼き鳥屋(地元商店)
- 焼そば屋、綿菓子屋、水風船屋(地元中学父親の会)
- 職能研鑽教室(6教室)
- パティシエ教室(料理教室講師である本校保護者)
- 寿司作り教室(地元寿司店)
- 大工教室(地元工務店)
- サッカー教室、ラグビー教室、ドッジボール教室(地元スポーツチーム)
- レクリエーションコーナー(3コーナー)
- ピンボール、千本引き(本校PTA)
- ストラックアウト(地元スポーツチーム)
- 無料体験コーナー(2ブース)
- 伝承遊び体験(地元非営利団体)
- モンキーブリッジ(地元ボーイスカウト)
- 職業斡旋所(1ブース)
- ハローワーク(本校PTAボランティア)
・・・つかれたので、以降は散文的に記載。
オペレーション
協賛者の募集・営業と調整
まず協賛者を募集。当然のとこながら募集だけでは協賛者は十分に現れないので、個別に営業をかける。
協賛者となった団体と調整を重ね、体験の粒を揃える。
強く意識したのは、協賛者にとってのメリットを提供する事。
・・・ぶっちゃけ、そんなものは無いのだけど、その意識を忘れると間違った方向に向かうという直感があったので、ここは必死に考えた。
団体管理表の作成
集まった協賛者は20。この量になると、さすがに手管理は厳しいので管理表を作成した。
協賛者の概要、募集要項、調整担当と進捗状況、受け入れ可能な人数、タイムスケジュール、必要な備品とその準備状況、当日の駐車場手配、衛生面でのリスクマネジメントなどなど、管理項目は多岐に渡る。
体験募集とアサイン
本校児童全員に対し募集をかけ、その結果に基づき体験のアサインを行う。
全校名簿を作成の上、これにあたった。無論、募集数と応募数には強い相関関係は無いので、調整には苦労する。
アサインの前提条件は以下の通り。
- 希望するもの最低1つにはアサインする
- 体験時間に指定のある児童については、それを配慮する
- 協賛先よりペアを組む指示のあったものについては、上級生と下級生をペアにする
体験内容の通知
体験先/回次が決定した子供たちに、名指しで配布する資料を作成。
通知内容は以下の通り。
- 体験先のブース
- 体験時間
- 集合場所
- 持ち物、留意事項
個別メンバー表
当日出欠確認のため、体験ブース・回次単位でのメンバー表を作成。
全体タイムテーブル
ハローワークでのアサインを容易とするため、全体タイムテーブルを作成し、各ブース/各回次の空き状況を記載した。
PTA会員に対する通知
当日の手伝い担当となっている会員に、当日の作業場所と作業内容を記した手紙を通知。
・・・はあはあ、こんな事書いていて本当に意味あるのか??
開催結果
参加児童数:約400名
体験のべ人数:約500名
模擬店:全て完売
負傷者・食中毒の報告:なし
開催翌々日に実施した委員会で保護者からの感想を聞いた。
いずれも、体験した子供たちが、何かしらの経験を持って帰って来た報告だった。
以下は一例。
- ダンス : インストラクターが本校の上級生で丁寧に教えてもらったので、すっかりリスペクトしてしまった。体験終了後も目を☆マークにしてインストラクターについて回っていて迷惑だったかしら?
- 消防士 : 消防服を着れるコーナーが事前に告知されていたけど、「そんな子供っぽいの、俺はやらない」なんて生意気な事を言っていた息子が、当日嬉しそうに着ていた。
- 寿司づくり : 自分で作った事が嬉しかったらしく、今まで食べなかった食材を食べていた。寿司屋さんの本物の包丁を触った事に感動していた。
- カフェ : ウェイトレスができた事が嬉しかったらしく、自宅でお茶を運んでくれた。
- 整体師 : 第一希望でなかったのが残念そうに学校に出向いて行ったが、帰宅するなり家族全員に整体体操をさせ、身体のゆがみを矯正してくれた。
これを成功と呼ばずして、何と呼ぼう。
運営を終えて
自分で言うのもなんだが、子供達にはとても貴重な経験をもたらす事ができたのではないかと思う。
最初の会長挨拶でも言ったのだけど、なにより20もの団体が協賛してくれたという事実が素晴らしい。他人の子供達の育成に携わってみようじゃないか、そう思う人々が、世の中にはこれだけいるのだ。
協賛者は一様に子供達の能力に感心していた。
事前に考案したオペレーションが大変なブースでは、協賛者は沢山のセーフティーネットを用意し子供の体験が崩壊しないような考慮をされていた。でも、その殆どは使われる事がなかったようだ。
きちんとしたインセンティブを与え、プログラムさえ組まれていれば、子供達は大人の想像を超える能力を発揮するのだ。
開催中、何人もの人に「毎年やらないのですか?」という質問を受けた。
でもね、これ、毎年やってたらね。
僕の本業が崩壊するよ。。
また、PTAの役員においては、僕の多忙や調整の不備などにより結構な作業量を強いてしまった。仲間だと思っているので敢えて謝ったりしたくはないが、この場を借りて労いの言葉を贈りたい。
というわけで、再来年、僕がまだPTAの会長だったら、またやります。
・・・いや、ちょっと考えさせてwww


















